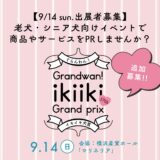目次
⾼齢者がペットと暮らすための課題
以前、このサイトでもお伝えした「⾼齢者がペットと暮らすための課題」。
 保護犬と高齢者のマッチングを目指して|赤坂サカス里親会
保護犬と高齢者のマッチングを目指して|赤坂サカス里親会
今回は続編をお送りします。 60 代・70 代のペットを新たに飼育したい意向のある⽅は全国に約282万⼈いるとされ、「飼いたいのに迎えられない」というギャップが社会課題となっています。 今回は、実際に老犬の保護犬を迎えた2組の里親さんに取材しました。
※わかりやすくお伝えするために「問題行動」と表記しています。
シニアの保護犬を積極的に迎える里親さんにインタビュー
先代犬はMダックス親子のホクトくんとヤマトくん。ホクトくんは18歳になり認知症が出始め、夜鳴きと徘徊で毎晩眠れない日々。一方のヤマトくんは9歳のときに椎間板ヘルニアと扁平上皮癌を煩い、車イス生活を送りました。
若い保護犬はすぐに手が上がる。でも、シニアは病気を持っていたりするのでなかなか決まらない。シニア期が大変なことはよく知っているけれど、それ以上にシニアのかわいさを知っている。だからそこまで推定10歳という年齢は気にならなかったし、自分達の年齢を考えれば逆にもう10歳以上の子がいいと思いました。
長生きダックスと自分達の年齢を計算
里親になろうと思った時、パパは60歳近く、ママは50歳に差し掛かる年齢でした。先代のホクトくんが18歳とご長寿だったこともあり、いまからパピーを迎えたら、パパは80歳を過ぎ、ママも70歳に近くなる。そう思うとこれからパピーを飼うのは難しいと判断。だからこそ、推定10歳の子は自分たちにピッタリだったのです。
高齢の保護犬を迎えて大変だったこと
レフトくんは人間に何かをされていた可能性があって、鼻にはずっと縛られていたような跡があったそうです。里親さん夫婦はそれまでの育ち方とかを知りません。
「まずご飯の時しかクレートから出てこないで、ご飯を食べるとさっとクレートに入ってしまう。ご飯とかをもらえてない子だったのかなっていうようなところがあって。水はカラになるまでひたすら飲み、新しく入れると、またひたすら飲み干すところがあったんです。だからある時に食べとかなきゃ、ある時に何かなきゃっていうのがある子だったから、そこがそこからお水をもう何10か所にも置いて、いつでも飲めるよういつでも食べられる量を置いたらすぐ治ったんだけど、何しろ犬のそういう行動を見たことがなかった。」
推定10歳で迎えた子を失った喪失感の方が大きかった
犬を家に留守番させなかった里親さん夫婦。レフトくんを迎えてから亡くなるまでの約6年間、毎日、里親さんと過ごしました。それでもパピーから飼っていた先代犬たちよりも喪失感は大きかったそうです。もっとこうしてあげたかった、ああしてあげたかったという思いが溢れ、2番目、3番目に迎えた子は、1番目の子以上にやってあげられることがあって、やってきたはずなのに…。
美味しいものや楽しいこと、それこそ何でもないお散歩でも楽しそうに歩くようになってどんどん表情が出てきた。やっと自己主張できるようになった。だからもっといろんなことやってあげたかったな、味わってほしかったなってという気持ちが喪失感につながっていったのです。
人間の健康寿命を考えたとき、元気でいられるのは「70歳まで」だと言ったパパ。そのとき65歳だったため、7歳、8歳で迎えるとなると、そこから10年後、自分達がどうなってるかと考えた時、少し厳しいと感じたそう。そしてご縁があってレフトくんを亡くしてから約1年後、14歳の保護犬もミニチュアダックスを迎えました。
2組目は、譲渡後に問題行動が出た保護犬の里親さんにインタビュー
ディディくんは飼い主さん死亡で福島県愛護センターに持ち込まれたときすでに9歳。大型で高齢、力が強いことから殺処分が決定していました。
しかし、とっても人懐こい性格で、すぐにゴロンとお腹を出してしまう子だったため、地元のボランティアさんから相談を受けた東京の保護団体が引き受けを決め、団体譲渡という形で殺処分をまぬがれました。ボランティアさんのところでは、言葉を理解し、おすわりやお手、伏せのコマンドもでききっと元の飼い主さんに可愛がられていたのだろうと推測されました。
ディディくんは未去勢だったので、すぐに去勢手術を受けました。その時、精巣部分に腫瘍があり一緒に切除。検査の結果は良性で、それ以外も特に問題ありませんでした。
ただこの時、足を拭かれるのはちょっと苦手だとわかったのです。
保護から約1ヶ月弱で里親が決定
ディディくんは初めてのセンターでの檻暮らし、預かりさん宅への環境の変化などで度々、下痢や嘔吐し不安を募らせていました。預かりさんの献身的なケアのおかげで、短期間で穏やかな生活ができるようになった頃、里親さんが決定。以前からこの保護団体にボランティア活動をされていた方でした。保護から新しいおうちが決まるまで、わずか1ヶ月弱でした。
保護犬を飼う難しさ
里親さん宅には先住犬で高齢のジャックラッセルテリアがいました。元々先住犬たちのトレーニングをウェルビードッグスクールで担っていた縁で、保護犬を迎えたいという相談をトレーナーの刈屋さんにしていた里親さん。先住犬との関係性も含めてカウンセリングに行き、特に 見当たりませんでした。
ところがある日、パパさんがディディくんにハーネスをつけようとして突然噛まれたのです。それまで預かり宅での病院通いで、嫌なことをされると脅しで口が出る傾向はあったものの、血が出るまで噛まれたことで、里親さん一家に「恐怖心」が芽生えてしまいました。
迎えた犬による問題行動の原因とは?
おうちに迎えてまだ日が浅く、ただでさえまだ信頼関係がない時に、ディディくんの急所に近い部分に触れてしまったことが原因でした。
保護犬に限らず人が噛まれてしまったら、それを問題行動と捉える方は多いかもしれません。極端な話、一度芽生えた恐怖心から、元の保護団体に戻したいと考える方もいるかもしれません。しかし、ディディくんの里親さん一家には、そんな選択肢はありませんでした。
ドッグトレーナーをつけてプロと一緒に問題行動の克服に取り組みました。
保護犬の怖がりを治す方法
そこで、トレーナーの刈屋さんが考えたのは、ハーネスはつけっぱなしにすることでお互いの安心を確保。まず離れたところから挨拶をして、ゆっくり近づき礼儀を重んじるように接しました。
元々甘えん坊で、触られるのは好き。でも足の近くや、腰から下、後ろ足やお尻の辺りを触ろうとすると警戒することがわかりました。もちろん、ブラッシングもNG。ブラシを見せるだけで唸って「やめろ」と意思表示をしてきました。
お手やお座りができていたので、遊びながらお手をしながら足を拭けるようにしたり、狩りの習性を生かしたおもちゃ遊びをしたりと、楽しみながら行うトレーニングが始まったのです。
保護犬が慣れるまでの期間はさまざま
里親さんが一番注意した点は、まわりの人たちに影響を及ぼさないようにすること。そのため、動物病院へ通う際もトレーナーの刈屋さんが同行しました。トレーニングや行動学、診療に関して理解のある獣医さんにお願いし、まず病院の待合室に座るだけで帰るという慣らしのトレーニングから始めました。そこから徐々に経験値を上げ、診察室に入って獣医さんからオヤツをもらうだけの日、オヤツをばら撒いた診察台に乗るだけの日など慣らしていく方法を取りました。
この慣らす方法は、ディディくんに、「嫌なことがないまま診察が終わった」という良い印象を持ってもらうことが目標です。
嫌なことをされると口が出るのがわかっていたため、里親さんもトレーナーの刈屋さんも獣医師に危害が及ばないよう時間をかけます。ワクチンを打つ時は、シリコン製のお皿のリックマットに缶詰などのペーストを塗ってペロペロ舐めてもらい、注射をしたり診察したり。オヤツが無くなりそうになると「先生ちょっとストップしてください」と刈屋さんが止め、ディディくんにも獣医さんにも里親さんにもなるべく安心安全で進められるようにしたのです。
トレーナーの刈屋さんとの二人三脚は功を奏し、保護団体のInstagramには、こう書かれていました。
体を拭かれるのが嫌だった(特に足)のですが、里親さんとトレーナーさんの努力のおかげで、背中や顔、ハーネス辺りまでは拭かせてくれるようになったとのこと!お散歩も随分とのんびりできるようになったし、遊びながらの訓練はとても楽しそう。先住わんことも仲良し。
よかったよー!嬉しいよー!
譲渡からわずか2ヶ月ほどでした。
警戒心の強い犬と仲良くなる先に見えてきたもの
里親さんはふとした時に「少し怖い」という恐怖心があったものの、少しずつ生活範囲を広げていきました。ドッグカフェの前まで来てのぞくだけ、入口の前でヤギミルクを飲むだけ、入りたいと意思表示をすれば席に座るなど、トレーナーさんがやったように慣らしていきました。
みんなで行ったバスツアーでは知り合いばかりでもドッグラン内はリードをつけたままのし念には念を入れた結果、ディディくんはママに絶大なる信頼を寄せ、かなりのママっ子になりました。
トレーナーの刈屋さんによると、犬も異性の人間を好む傾向があり、今回ディディくん宅には、メスの先住犬とパパ、ママ、娘さん。そして担当の獣医さんも女性だったことも功を奏したのではと分析します。だからといって男性が苦手なわけではなく、朝の散歩ではディディくんに会えることを楽しみにしてくれている高齢男性を見つけると、お尻をフリフリしながら大喜びで駆け寄っていくようになりました。
そして恐怖心を抱えながらもディディくんとの接し方や距離感のコントロールが上手だった点も大きかったと言います。ただ撫でるだけでは慣れるわけはなく、撫でられた時、少しでも嫌な経験があったり、単に振り回されるだけだと、だんだん嫌だなという気持ちが増えていく可能性もある。その点を、ママが接触する相手を吟味して「一人ずつ撫でてください」とか、「片手で撫でてください」というようにディディくんに対する配慮が適切だったと刈屋さん。
ブラッシングひとつをとっても「心地よいものだよ」と伝える時に、優しくゆっくり撫でる、心地よく撫でることの伝え方が大切になってきます。撫でられるのは好きでも、OKゾーンとNGゾーンがあって、譲渡時はNGゾーンの方が広かったのですが、それを徐々に徐々に慣らし、「NGゾーンも気持ちいいんだよ」と、だんだん増やすことで、接触することが心地よいものだということを自然に伝えられたんだと思います。
いまでは、トレーナーの同伴なしで動物病院にも行けるようになったディディくん。ママにデレデレの毎日を穏やかに過ごしているそうです。